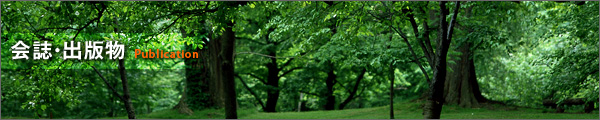虫ぎらい卒業
虫めがね vol.37 No.4 (2011)
「虫ぎらいは保育士として失格です!」
筆者が担当している保育士・幼稚園教諭養成コースの授業の冒頭で、いつもこのように宣言することにしている。学生たちは一様に、
「この先生は何をふざけた事を言っとるんや。たかが虫くらいで大げさなことを言っとる」
とでも言いたそうな顔をして聞いている。
小さな子ども達は虫、動物、草花、にじ、雪など身近な自然現象に興味を持ち、それによって知的好奇心や考える力を身に付けていく。過去の幾多の科学者たちも、子どもの頃は昆虫少年だったと語っている例は多い。ノーベル化学賞を受賞された福井謙一博士も、子どもの頃は自然の中で自由に飛びまわって遊んだと述べられている、と話す。テレビや絵本でいくら沢山の虫、動物、草花などの知識を得ても、それらは疑似体験であり、奥深い知的好奇心は十分には育たない。
皆さんが保育士や幼稚園の先生になった時に、子ども達が、捕まえてきたバッタをポケットから取り出して、
「先生、これ何の虫?」
と差し出した時に、
「ヒャー、気持ち悪い!早く逃がしてあげなさい」
と言ったら、せっかく芽生えようとしている将来のノーベル賞科学者になるかもしれない子ども達の知的好奇心に水をかけることになるのですよと教える。
そして、その後の授業の中で虫を手にとって細部まで観察したり、スケッチしたり、ダンゴムシを取りに行き、捕まえたダンゴムシを使って徒歩競争をさせたりする。また、セミを手に取り、鳴き声を出す器官はどこかな、オスとメスはどこで見分けるのかな、などと体験していく。
「セミの鳴き声はただうるさいだけだと思っていたが、よく聞くと種類によって鳴き方が違うことを知りました」
「ダンゴムシをこれほどじっくりと観察したことはこれまでなかった。小さな脚が一四本もあって、一所懸命歩いており、意外と可愛いのに気がつきました」
という学生もいる。
若い学生たちは素直なので、卒業の頃になると、ほとんどの学生たちは虫ぎらいを卒業する。なかには、
「先生、最後まで虫は好きになれませんでした。でも、虫を触さわれるようにはなれました」
と言って卒業していく学生もいる。
(赤タイ)
ドングリの木
虫めがね vol.37 No.1 (2011)
「ドングリという名の木はありません」
毎年秋になると学生たちと大学近くの公園にドングリ拾いに出かける。自然観察授業の一環である。出かける前にドングリについての基礎知識を説明する。ドングリはブナ科植物の果実であり、日本には五属二一種がある。そのうち八種類くらいはアク(渋)抜きしなくても、蒸したり、炒めたり、粉にして団子にして食べられる。栗もドングリの仲間ですと言うと、「へー」と意外な顔をしている。日本に稲作技術が入ってくる前の縄文時代の日本人にとってドングリは大切な食料であったと話す。そして、食べても渋くないドングリの見分け方を説明する。筆者が子どもの頃はドングリを食べた経験があるが、いまの若者たちはドングリを食べたことがないようだ。
毎年ドングリ拾いに出かけているのだが、いつもは木の下にびっしりとドングリが落ちていたものが、今年は落果の数が少ないようだ。今夏の異常猛暑のせいであろうか。ドングリを食料としている動物には、人間以外にも、熊、ネズミ、リス、タヌキ、カケスなどがいる。今年は東北・北陸地方などで、熊が人里に現れ、事故を起こしているというニュースが多いようだ。メスの熊は冬眠中に出産し、子熊に乳を与えて保育しなければならない。熊にとっては、秋のこの時期は冬眠まえのエネルギーを体内に蓄える大切な時期である。その為の大切な食料であるドングリが少ないので食べ物を求めて、熊は人里にやって来るのだろう。人里に下れば、残飯や農家が植えたリンゴ、ブドウ、トウモロコシなどにありつける。
先日、四歳半になる孫がわが家に遊びにやって来た。裏の小山にドングリを拾いに出かけた。「どんぐりころころ」の童謡があるようにドングリは子ども達にとって身近なものである。「あ!ここにあった。ここにも!」
と喜んで拾っている。マテバシイやスダジイを拾って、家に持ちかえり、フライパンで炒めて食べた。筆者も子どもの頃に食べた記憶がよみがえり、なつかしく食べた。栗とは異なる甘みがあっておいしい。縄文人を孫と一緒に体験したわけだ。「おいしい?」と孫に尋ねたら、「うん」と素直にうなずいていた。
(赤タイ)
虫を歌う
虫めがね vol.37 No.3 (2011)
万葉集にも蚊やりについて歌った和歌があり、ハエ・蚊・ノミなどの害虫は昔から私たちの生活の身近に居たことが判る。ゴキブリは江戸時代の南蛮貿易により南の国から堺の港にやって来たと考えられている。今では私たちは、蚊取線香、殺虫エアゾール、ノミ取粉など、これらの害虫と戦う手段はいろいろ持っているが、江戸時代の庶民はどのようにこれらの害虫をふせいだのだろうか。
蚊帳[かや]、蝿帳[はいちょう](ハエが入らないように網で囲った箱)、蚊やり・蚊燻しなどが江戸時代に使われていたことは記録にも見られる。蚊やりや蚊燻しには今の蚊取線香のような殺虫力は無かった。乾燥したカヤ、杉、松、ヨモギなどの葉や、ミカンの乾皮などを燻して蚊を追い払った。これらは煙が多く、眼や鼻の粘膜を刺激する割には蚊に対する効果は余りなかったと考えられる。
庶民を悩ましたこれらの害虫を敵として憎んでいたかというと、そうでもない姿が見えてくる。かれらは害虫であるが、人間生活の共存者として受け入れていた様子が浮かびあがってくる。
江戸時代後期の俳人・小林一茶に、「やれ打つな ハエが手をする足をする」
という有名な句がある。ハエを叩いて殺そうなんて可愛そうではないか。ハエをよく見ると、足を擦り合わせて命乞いをしているようではないかと歌ったものだ。
イエバエはよく見ると前脚、後脚を擦り合わせたり、後脚で翅をこすったりしている。これは自分の身体についているゴミやダニなどを払い落として身体を清潔にしている身繕いの仕草である。
また同じ一茶の句に、「ノミどもに 松島見せて放ちけり」
という句がある。一茶が宮城県を旅していたときに尿意をもよおしたので、路傍でフンドシをほどいて立ち小便を始めたら、フンドシに潜んでいたノミが日本三景の一つ・松島を眺めているという何とも一茶らしい句である。他にも、「ノミ焼いて 日和占う山野かな」「蚊やりから 出現したりでかい月」
などがあり、庶民派の一茶らしい句である。
また、江戸時代前期の俳聖と言われている松尾芭蕉にも、「ノミ・シラミ 馬の尿ばりする枕もと」という当時の庶民の生活を描いた句がある。
外国にもメキシコには、La cucaracha(The cockroach)というゴキブリを歌ったラテン調の愉快な民謡がある。
人々にとって悩ましいハエ・蚊・ゴキブリ・ノミ・シラミなども、歌にうたって、笑い飛ばす庶民のしたたかな生活の力がうかがい知れる。
(赤タイ)
天然食品は安全なの?
虫めがね vol.37 No.2 (2011)
「当社の食品はすべて天然のものを材料としており、合成化学品は一切添加しておりません。従って安全で身体に良い健康食品です」
このような食品のPRをテレビや新聞、雑誌などで多く見かけるが、いつも不思議に思っている。このような説明を行っている人に、
「なぜ、天然物は安全なのですか?」と尋ねたいと思っている。
予想される一つの返答は、
「天然物はもともと自然界にあったもので、神様が作ったものです」
と言うことだろうか。神様は間違ったことをしないのだろうか。危険な物を作らないのだろうか。もともと自然界にあって神様が作ったものでも、毒フグ、毒キノコ、黄変米など、危険な食べ物は沢山ある。また、
「なぜ、合成化学品は危ないのですか」
とも尋ねたいと思っている。想定される答えの一つは、
「合成品は人間が作ったものです。人間は間違いをおかすので、危険なものもつくる」
であろうか。また、
「もともと自然界にあったものでないので、未知の物、未経験の物への不安がある」
という心理的不安も考えられる。これは人類のDNAに植え付けられた本能的なものであろう。
人々が喜んで、何の抵抗もなく受け入れている種なしブドウはブドウの開花の前後に、ジベレリンという化学薬品(農薬)で処理して人工的につくったもので、自然界にあったものではない。おいしいお米として多くの消費者に受け入れられているコシヒカリ、ササニシキは、どちらも人工的に品種改良されて出来た物で、神様がお造りになった物ではない。でもこれらが人工物質なので危険な食品ですと説明されているのを聞いたことがない。
「天然物は安全で、合成化学品は危険です」
これは間違った迷信です。冒頭の食品会社のPRはこの迷信を巧妙に使って消費者に取り入っていると言えよう。
(赤タイ)