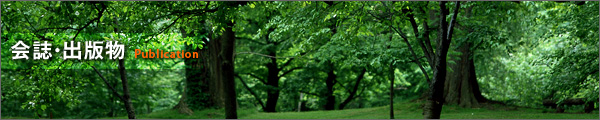生物たちの結納金
虫めがね vol.41 No.1 (2015)
若い男女が結婚に至るまでの一つのプロセスとして、日本の習慣では結納と言うのがある。これはもとは皇室の宮中儀礼として始まったらしい。それが室町時代に公家や武家社会に広がり、江戸時代末期から一般庶民の間にも広まったと言われている。古くは新郎家から新婦家へ、当時、貴重品であった帯や着物類を贈ったらしいが、最近の若いカップルはお互いに相談して結婚指輪を交換したり、両家で顔合わせの食事会をやって、結納に代えるなど、古い形式にとらわれないやり方が増えているようだ。
結納の習慣は日本だけでなく、外国でもあるようだ。イスラム社会にマフル(mahr)と言うのがある。マフルは現金や宝飾品や不動産など、かなり高額なものを新郎側が新婦側に送る。これが高額なため、結婚志願の若者は一生懸命に働いてお金を貯めねばならない。それで、経済的に豊かでない若い男性は、いつまでたっても結婚できないと言うことが起こる。逆に、資産家の男性は複数の女性と結婚(一夫多妻)することも起こる。
結納というのは人間だけでなく、ある種の昆虫にもある。北米東部の森林地帯に生息するツマグロガガンボモドキやハルノオドリバエのオスは、メスに求愛する前に、ユスリカ、ガガンボなどの小昆虫(求愛餌)を捕まえてメスに近づく。メスに近づくとその餌を差し出す。メスはオスが持参した餌が小さいと相手にしない。大きいとそれを受け取って、食べることに夢中になる。メスが食べている間に、交尾が行われ、オスとメスの結婚が成立することになる。求愛餌の大小、良否がメスを獲得する成否に直結する。
野鳥の仲間でモズやカワセミ、コアジサシなどは、オスが餌(求愛餌)を口にくわえてメスに近づき、差し出す。メスはその餌が気に入れば口移しにもらって食べる。こうして、親密な関係になった後に、交尾が行われる。カワセミの観察では、たった一回の餌の提供では親密になれず、数回餌を運びつづけて、ようやくメスに気に入ってもらうこともあるようだ。
メスには子を産み育てるという生物にとっては最重要の任務がある。出産には多大なエネルギー(栄養分)を必要とする。其の為の準備として、オスから餌をもらい、体内に蓄えることは健全な子孫を残すために必要な作業であろう。オスはメスのこの任務を達成する為に、骨身を惜しまずに協力しないといけない。
(赤タイ)
デング熱と鎖国政策
虫めがね vol.40 No.6 (2014)
今年の夏に、日本ではすでに無くなったと考えられていた熱帯性のデング熱の患者が見つかって、新聞やテレビで大きく報道された。患者はいずれも海外渡航歴はなかった。更に、数名の患者が見つかり、調査の結果、これらの患者は共通して、東京渋谷区の代々木公園内でヤブ蚊(ヒトスジシマカ)に刺されていることや、代々木公園内で捕獲されたヒトスジシマカからデング熱のウイルスが検出されたことなどで、代々木公園で感染したことが明らかになった。その後、東京都に隣接する千葉県の公園や兵庫県西宮市などでも感染例が見つかるなど、全国的な広がりを見せている。
現在のようにグローバル化した社会では、地球の反対側にあるアフリカや、南米からでも、二四時間以内に日本に来訪できる。大勢の外国人が日本にやって来ているし、また、大勢の日本人が外国に出かけており、そこで何らかの感染症にかかり、発症前に日本に帰国し、帰国後に発症する可能性も大きい。つまり、人の交流のグローバル化は、感染症もグローバル化すると言うことである。
今から約三五〇年前(一六六四~一六六五)に、ロンドンでネズミノミが媒介するペストが大流行した。最盛期には毎週六千~七千人のロンドン市民が亡くなった。この「ロンドンの大疫病」は、当時のロンドンの人口約四十六万人の二十%あまりが消滅するほどの大流行であった。この疫病は、その後、ドーバー海峡を渡り、大陸に波及し、ドイツ、オランダ、ベルギー、オーストリア、ハンガリーなどへ飛び火し、そこでも大勢の人々が亡くなった。
当時の日本は徳川幕府の施政下にあり、厳しい鎖国政策をとっていた。日本に来航できる外国船は中国船かオランダ船に限られていた。寄港できる港も長崎の平戸港に限られ、来訪した外国人の居住地も長崎の出島に制限した。これらの厳しい鎖国政策は、当然、海外からの感染症の流入を大きく阻むことになる。徳川幕府は自分の政権を長期に安定的に守る為に鎖国政策をとったわけだが、この政策は外来性感染症から日本国民を守る効果があったことになる。
日本国内にペストが初めて上陸したのは、徳川幕府が崩壊し、鎖国から開国政策に切り替わった明治時代に入ってからである。
(赤タイ)
ホタルにも方言がある
虫めがね vol.40 No.5 (2014)
近ごろはホタルを見ることは極めて少なくなった。今では、ホタルが見られる場所は、「ホタルの里」とか言って、観光客にPRしている。私が子どもの頃に育った福岡の田舎では、我が家の前を流れる小川には、夏になると毎晩ホタルがたくさん飛んでいた。最近、久しぶりに田舎に帰って尋ねると、今ではその小川ではホタルは見られないそうだ。ホタルが見られなくなった原因として、農薬や洗剤などの化学物質が疑われているようだが、それも否定はできないが、むしろ川の護岸工事などで、ホタルの幼虫の餌となるカワニナなどの貝類が生息できなくなったことが大きい。
子どもの頃、夕食を済ますと、うちわを持って、前の小川に行き、「ほーほーホタル来い、あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞ」と蛍狩りに行ったものだ。金網で作った蛍籠を持って行き、捕まえたホタルをその籠に入れ、水辺のホタル草などを入れて持ち帰った。餌として、砂糖水を浸み込ませた脱脂綿を入れておけば、家でもしばらくの間はホタルのほのかな光を楽しむことが出来た。
小川などで、大きなホタルが光っているのはゲンジボタルである。ホタルは光をコミュニケーションの手段にしている。オスはピカリ、ピカリと光りながらメスの光を求めて飛び回る。メスに対して求愛の信号を送っているのだ。そして、メスを見つけると近くに止まり、パッパッと短い間隔で光を点滅させる。メスがこれに答えてパッと一回光れば、求愛が成立する。ここで、メスからの応答がなければ、オスはあきらめて飛び去るしかない。
ホタルが光るのは、ルシフェラーゼという酵素の働きでホタルの体内でルシフェリンが酸素と結合し、オキシルシフェリンに変化する。その時に生じるエネルギーが光エネルギーに転換して蛍光を発する。これは熱を介していないので、風や水で消えず、手で触っても熱くない。むしろ冷たく感じる。
ゲンジボタルのオスが同じ木に沢山集まり、集団で同時に発光することがある。この時の点滅間隔は、西日本では二秒間隔、東日本では四秒間隔と、地方によって点滅間隔に違いがあることが分かっている。境界の長野県付近では中間の三秒型もいる。ホタルにも東京弁と関西弁と言うような、方言があるようだ。ホタルの世界では、関西より関東の方が点滅間隔が長くのんびりしているのだろうか。
(赤タイ)
あなたの家にノミはいませんか
虫めがね vol.40 No.4 (2014)
先日、テレビを見ていると一家に猫を八頭も飼っている家庭が紹介されていた。この家庭は子どもがいないなどの事情があったが、最近は犬、猫を飼育している家庭が増えたのは確かである。生活レベルの向上や少子化の影響でペットを飼う家庭が増えたのであろう。私が子どもの頃は犬は番犬であり、猫はネズミ取りであるという考えであったが、今では家族の一員としてペットを飼っている家庭が多い。ペットによって精神的な安らぎを得る面が評価されているわけだ。
家族の一員だから、買い物に出かける時には、乗用車に乗せて出かけ、家に戻ると室内で飼う。テレビを見る時も犬を横に置いて一緒に見ている。寝るときは同じベッドで寝る人もいる。このような飼育習慣の変化により、ノミは一時期忘れられかけた害虫であったが、再びその被害を多くしている。
うちの犬はいつも清潔にしているのでノミは居ないと思っていたが、先日ノミが見つかった。きっと犬の散歩中に近所の犬とじゃれついている時にもらったのだろうと考える人も多いだろう。だが、カリフォルニア大学(米国)のラスト教授の実験では、ネコ同士がじゃれて体を接しても、他方へノミが移動することは少なかった。同じように、ノミがついている猫を人が抱いたくらいではノミは人体へ移ってくることは少ない。ノミは宿主嗜好性がはっきりしているので、猫についているネコノミは猫の血液や体温を好むわけで、わざわざ猫から離れて人に移ることは少ない。
野良猫や野良犬などが棲みついている場所や、彼らの通り道となる公園の草むらや砂場などを飼い犬が通過すると、そこに潜んで待機していたノミがジャンプして犬に飛びつく。飼い犬や猫がノミをもらうのはこのケースが多い。
ネコノミは卵→幼虫→蛹→成虫と完全変態をする。人を吸血するのは成虫だけだが、成虫の寿命は約一ヶ月である。しかし、成虫になる直前の蛹の寿命は長い。寒いとか乾燥などの外的環境が悪い時や、ノミが吸血しようとする動物が現れない時には、飲まず食わずのままで半年でも一年でもじっと待機している。そして人や動物が近づくと直ちに繭の殻を破ってジャンプして飛びつく。この時のノミのジャンプ力は体長の約百五十倍も飛び上がることが出来る。これを身長一六五㎝ の人にたとえると、約二五〇m の高さに飛び上がることになる。このようなノミの生きるためのメカニズムには驚くほかない。
(赤タイ)
ゴキブリは群れているのでイヤ
虫めがね vol.40 No.1 (2014)
仲間で群れて生活している生き物は多い。カラスやスズメが群れをなして空を飛んでいたり、木に止まっている様子は良く見かける。シマウマやバッファローが集団で大移動している光景などを、テレビや映画で見たことがある人も多いだろう。また、小さな魚も何千尾も集団で泳いでいることがある。このような大群ではないがゴキブリも仲間で集まって生活している。ゴキブリの糞に含まれる集合フェロモンによって仲間を呼びあつめているのだ。
大学の学生約一八〇人に「嫌いな虫はなんですか」とアンケートを取った。その結果、ムカデやクモを挙げた学生も多かったが、断然群を抜いてゴキブリがトップにあった。「なぜゴキブリが嫌ですか」との質問には、群れているから嫌という回答もあった。たしかに、ぎらぎらと脂ぎって、光沢のあるゴキブリが集まっているのを見るのは気持ちが良いものではない。しかし、ゴキブリは何となく群れているのではない。それなりの理由がある。群れることによって乾燥や寒さに対する抵抗力が高まる。また、一匹で生活するより仲間と一緒に生活すれば、餌にありつける確率や配偶者に巡り合えるチャンスも高まる。京都大学の石井教授らのチャバネゴキブリの実験では、一匹で飼育した場合より複数匹を一緒に飼育した方が成虫になるのが早かった。
人類も発生以来群れて生活する習性をもっている。発生当初は家族、親族程度で群れていたのだろうが、その群れは歴史とともに大きくなり、部族、種族で固まり、今では国家という大きな集団で生活している。人類もゴキブリと同じように一人っ子よりも兄弟が多い方が成長が早いのであろうか。人の場合、そのような研究例は無いが、一人っ子であっても、幼稚園に行き、小学校、中学校に行って、集団の環境で育つのでゴキブリのような結果にはならないだろう。
ゴキブリが群れて生活する理由のもう一つは、野外ではカエルやネズミ、野鳥などの天敵に襲われにくいこともある。一匹で行動しておればカエルにとって攻撃ターゲットは絞られるので、近づいてペロリであるが、群れていればカエルも近づき難い。近づいてもどれから攻撃してよいのか、きっかけをつかむのに困る。カエルはまず、群れ全体に攻撃をしかけてみる。おどろいたゴキブリが大騒ぎして、群れから外れて一匹で動いているゴキブリを見つけたら、それを目がけて攻撃し、ペロリとたべる。
(赤タイ)